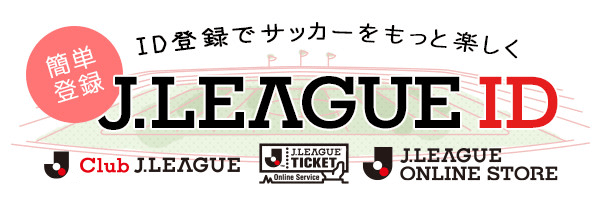この試合から岐阜はいつもの【3-4-2-1】から【3-4-1-2】へシフトチェンジ。それに対し、福岡は右サイドバックに本来は中盤からFWをこなす三島勇太を置き、右FWに中での勝負強さがある城後寿、センターには裏への抜け出しを得意とする坂田大輔を置いて、左のFW石津大介、シャドーの金久保順の2人を中心に、左で起点を作ってから、スペースができた右サイドを効果的に突いて、最後は中央で勝負をするという、攻撃の形を明確に持った戦い方で挑んできた。
立ち上がりこそはこう着状態が続いたが、福岡の左サイドでボールが収まりだすと、徐々にペースは福岡の下に。そして13分、福岡の狙いが見事にはまった。サイドからのサイドチェンジを中央で城後が受けると、右サイドをオーバーラップした三島に左ウイングバックの染矢一樹がケアした瞬間、空いた右サイドバックのスペースに、CBのパク ゴンがすっと入り込む。染矢の判断は間違っていなかったが、CBを見ているはずのツートップの守備意識が希薄になってしまっていた。城後からフリーのパクにパスが通ると、パクはノープレスの状態で、DFラインの裏に飛び出したFW坂田大輔にピンポイントクロス。これを完全にフリーの坂田がヘッドで決めて、福岡が先制に成功した。
その後も福岡は同じような形で攻めてくると、岐阜のDFラインが下がりだし、今度は福岡の前線からのプレスも効力を発揮し始める29分、福岡の前線からのプレスに差し込まれ、デズモンドがペナルティーエリア内でFW石津大介にボールを奪われ、決定的なシュートを打たれるが、これはGK時久省吾がファインセーブ。岐阜はなかなか攻撃の糸口がつかめないまま、前半を0-1で折り返した。
後半、岐阜もウイングバックを高い位置に張り出させ、攻勢に転じる。福岡は立ち上がりこそ差し込まれたが、再びリズムを取り戻すと、57分には石津に代えて、FW金森健志を投入。裏への爆発的な飛び出しが得意な期待のルーキーを投入したことで、「どんどん裏に仕掛けろ」というプシュニク監督の強烈なメッセージをチーム全体に伝えた。
このメッセージ通り福岡は、両サイドを広く使った攻撃から、裏に素早く入れるサッカーを展開。攻撃意識を強めたことから、岐阜にもカウンターチャンスが生まれた。60分、左サイドを破ったFW樋口寛規のピンポイントクロスを、中央で新加入のヴィンセント ケインがフリーでヘッド。しかしミートしきれず、ゴール左外へ。樋口からの最高のボールだっただけに、ここは決めてほしかったし、ここを決めていれば、福岡の攻撃のリズムは断ち切れていただけに、決めきれなかったことは痛恨だった。
63分、城後がバイタルエリアで冷静に落とすと、フリーの金久保が冷静にペナルティーエリア外から右足を振り抜いて、ゴール左上隅に突き刺し、勝負あり。
67分、左サイドの野垣内俊のクロスを、ファーで杉山新がヘッドで合わせるが、これはGK神山竜一のファインセーブに阻まれた。さらに左からの崩しで、ファーでデズモンドのところにチャンスボールが来るが、決めきれなかった。
77分、左ショートコーナーから、染矢が豪快に狙うも、これはバーに嫌われた。逆に80分、中原秀人のスルーパスから金森に抜け出されるも、シュートはGK時久がファインセーブ。87分、樋口からのスルーパスに染矢が抜け出し、放ったシュートはGK神山にはじかれるも、詰めていたド・ドンヒョクの下へ。しかし、渾身のシュートは枠をそれていった。90分にもド ドンヒョンが中央でシュートを放つが、ミートしきれず。決定機はいくつも作った。しかし、決めきれない。
「チャンスはあったけど、決めきれない。そういう差が出た」と行徳浩二監督は語るが、もっと深刻なのはその前にある。当然チャンスをモノにできない決定力のなさが敗因の一つではあるが、最大の要因ではない。最大の要因は試合運びが後手を踏みすぎたこと。ピッチ上で福岡の狙いを感じ取って、しっかりとリカバーできなかった。しかも決定機を作り出せたのは、いずれも先手を取られてから。特に0-2になってからのチャンスが多かった。当然、攻め込む時間が終盤になると、焦りや細かいミスが増えるし、カウンターのリスクはグンと上がる。一か八か的なサッカーになると、たとえ逆転できたとしても、サッカーとして、チームとして成熟しきっていないことを指す。それではチームは一向に成長はしない。だからこそ、ちゃんとした90分のオーガナイズの上でサッカーを展開してほしい。
試合後、岐阜サポーターから大きなブーイングが飛んだ。昨年、アウェイの町田で敗れた時も、今年G大阪にホームで大敗をしても、全体でブーイングをしなかった彼らがそういう行動をとった。この意味をクラブ全体として重く受け止めないといけない。もしかすると、一番今の状況に危機感を感じているのは、サポーターなのかもしれない。
以上
2013.07.21 Reported by 安藤隆人